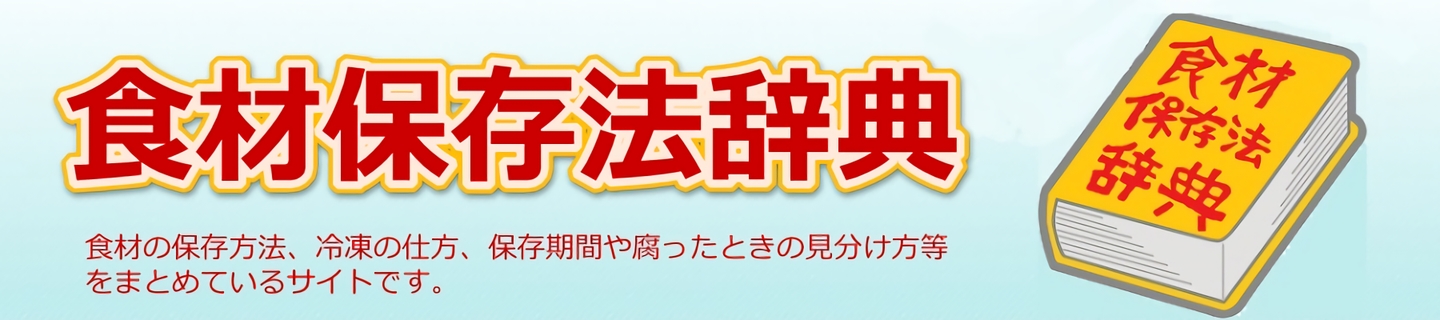きゅうりの保存方法 カットした場合は? 塩もみや冷凍する方法も紹介!

わたしはダイエットをするときはいつもきゅうりを食べるようにしています。
サラダにしてもお漬物にしても和え物にしてもなにしても飽きなくおいしく食べられるきゅうり。
ついついスーパーへいくと、たくさん買ってきてしまう食材のひとつであります。
今回はたくさん買ってきてしまったきゅうりを長くおいしく保存する方法をお伝えします。
きゅうりの保存方法
きゅうりは基本、野菜室で保存をします。
冷蔵庫の野菜室で保存する方法
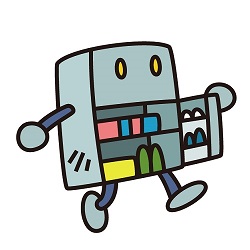
- まずは買ってきたきゅうりを1本ずつキッチンペーパーなどで包みます。
- そして、キッチンペーパーで包んだものを、さらにラップを使って全体を包みます。
- ラップでくるんだきゅうりは野菜室に立てて保存をします。
冷蔵庫の開け閉めをするときに、冷蔵庫の中できゅうりが倒れてしまわないように、カップやパックなどを使って保存するとよいです。
高さのあるパックなどにラップでくるんだきゅうりを立てかけるか、きゅうりが入れられる長い容器をつかいましょう。
きゅうりは、野菜室で保存しても約4、5日が目安です。
きゅうりは、縦に伸びる野菜なので、保存するときも縦にすると長持ちをするそうです。
カットしたきゅうりの保存方法

カットしたきゅうりを保存する方法は、カットした断面に空気が触れないように、しっかりとラップをして野菜室で保存します。
さらに密閉できるジッパーや蓋付きの保存容器に入れて保存するとよいです。
カットをしてしまうと、あまり長持ちしませんので、できるだけ早く食べるようにしてください。
カットしたきゅうりの保存期間は1〜2日が目安になります。
きゅうりを塩もみして保存する方法

カットしたきゅうりを長持ちさせたければ、切ったきゅうりを軽く塩もみすると長持ちします。
塩もみしたきゅうりをジッパーなどに密封させて入れて野菜室で保存してください。
塩もみして保存したきゅうりはサラダや和え物におすすめです。
我が家では、大根やきりこんぶなどとも一緒に塩もみをしてお漬け物のようにして食べます。
とても美味しいです。
使うときには、一度水洗いしてから使いましょう。
塩もみをしておくと、1週間ほどに保存期間が伸びるので、おすすめです。
きゅうりは冷凍できる?
きゅうりは冷凍保存もすることができます。
きゅうりは冷凍保存をするときはカットをしてから保存してください。
- まずきゅうりを輪切りにカットして、全体に軽く塩をふりもみこみます。
- 水気をきっちひしぼったらフリーザーバッグやジッパーなどの、蓋付きの保存容器に入れて平らにして、冷凍庫で保存しましょう。
冷蔵庫で保存した場合は約1カ月ほど保つことができます。
きゅうりの保存期間はどれくらい?

きゅうりはラップしてたてて野菜室で保存すると4.5日。
カットをしてしまった場合は1.2日なので、塩もみをして1週間ほど保存できるように工夫します。
カットして塩もみをして冷凍で保存をした場合は約1カ月ほど持つのでたくさん買ってしまった場合は冷凍保存もおすすめです。
きゅうりは腐るとどうなる?
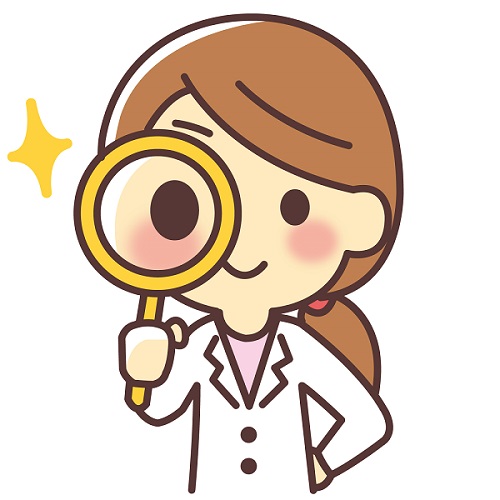
きゅうりの新鮮さはトゲトゲが痛い物が新鮮。
だんだんトゲトゲが丸みをましていくけどまだ食べれます。
持ったきゅうりのトゲトゲがつるつるにかわるまで大丈夫。
そこから痛み始めます。
まず皮から元気がなくなります。
ここはまだ食べられる範囲。
しなっとしているならギリギリ大丈夫。
皮がしなっとして、触るだけで皮がむけたら要注意!
だいたい上下から腐り始めるので上下はきりおとしてまだ真ん中は食べれます。
心配なら冬瓜のように皮をむいてスープにして食べるのもいいです。
完全にアウトは持ち上げると曲がる!
これは完全に腐ってます。
大人しく捨てましょう。
きゅうりが余ったときのオススメレシピを紹介!
夏野菜の代表格といえばきゅうりです。夏になると安売りしているので、つい大袋で買ってしまいます。
また、きゅうりは一度にたくさん収穫できるため、大量に貰うこともありますよね。
とはいえ、メインのおかずにはならないですし、サラダにしてもたくさん食べることもできず、余らせてしまうことも多いのではないでしょうか。
そこで、きゅうりがおいしく、たくさん食べられるレシピを紹介します。
1. きゅうりのビール漬け
ご飯がすすむお漬物です。
漬物にすると日持ちするのが嬉しいですよね。
ビールのアルコール分は漬けている間に殆どとんでしまうようですが、子供が食べるなどで心配な場合はノンアルコールビールでも作れますよ。
材料
- きゅうり 5本
- ビール 100cc
- 砂糖 90g
- 塩 30g
作り方
- きゅうりはヘタを切り落とし、長さを半分に切る。
- ジップロックなどのビニル袋に全ての材料を入れ、軽く揉む。
- 冷蔵庫に入れて保存する。1日後から食べられ、1週間を目処に食べ切ります。
2. きゅうりの中華炒め
きゅうりを加熱することでたくさん食べられます。
男性ウケも良い中華風の味付けです。
材料
- きゅうり 2本
- 乾燥わかめ 大さじ1弱
- しょうが ひとかけ
- にんにく ひとかけ
- ごま油 大さじ1
- 鶏がらスープの素 大さじ1
- 塩・胡椒 適量
- ラー油 適量
作り方
- きゅうりは長さ5cmくらいの食べやすい太さの棒状に切る。
- しょうが、にんにくはみじん切りにする。
- わかめを戻しておく。
- フライパンにごま油、しょうが、にんにくを入れ、香りが出るまで炒める。
- きゅうりと水気を切ったわかめを入れ炒める。お好みですが、歯ごたえがしっかり残る程度にさっと炒めると美味しいと思います。
- 鶏がらスープの素を入れる。味を見て、塩・胡椒で味をととのえる。
- ピリ辛が好きな方はラー油をかけても美味しいです。
3. 香味きゅうり
茗荷と青紫蘇の風味が食欲をそそる、さっぱりとした浅漬け風の一品です。
材料
- きゅうり 2本
- 茗荷 2個
- 青紫蘇 5枚
- 麺つゆ 大さじ1
作り方
- きゅうりは乱切りにして、軽く塩(分量外)を振る。
- 茗荷、青紫蘇はみじん切りにする。
- 水気を切ったきゅうり、茗荷、青紫蘇を麺つゆで和える。冷蔵庫で1時間ほど味をなじませる。
関連ページ
- ジャガイモ
- 私は料理初心者の頃、よくジャガイモを余らせていました。 ジャガイモは袋売りで買ってくると、必ずと言っていいほど残ります。 私は揚げ物もやらなかったので、フライドポテトという選択肢はなく、早いときには翌週になると栽培ができるのではないかというくらい芽が生えてきていました。 そんなジャガイモの使い方、保存方法をまとめてみました。
- にんじん
- にんじんはなんとなく日持ちしそうなイメージがあったので、買ったときのビニール袋に入れて冷蔵庫においておいたところ、次に使おうとしたときには溶けたようにどろどろになっていて悪くなっていたのです。 にんじんは意外と日持ちしないということ、水気に弱いということをこのときに知りました。 このときの経験を活かしてにんじんの保存方法をまとめたので、どう保存すればいいんだろうと思っている人は参考にしてみてください。
- 玉ねぎ
- 私は5年ほど飲食店で調理関係の仕事をします。 たまねぎは数多くの料理にも使用される万能のお野菜であり当然大量に仕入れるのですが、一見するとどのように保管してもよさそうに見えるこの野菜。 私はどうも今まで誤った認識で保管していたらしく上司に怒られてしまいました。 その際に本当の玉ねぎの適した保存方法というのを調べたので、今回料理人流玉ねぎのおいしい保存方法を伝授させて頂こうと思います。
- キャベツ
- キャベツは1人暮らしの人にとって、丸ごと1個買うだけでずっとキャベツが続いてしまうと思います。 そして冷蔵庫も丸ごと1個入れると他の物が入らないケースもあると思います。 私は、そんな経験をしてきました。 しかしキャベツの保存方法を工夫すれば冷蔵庫を占拠する事なく便利で使いやすい、食材に変わるのでキャベツ中心に保存方法を紹介します。
- レタス
- 癖のないレタスはサラダだけではなく、チャーハンやお味噌汁にも活用ができる野菜です。 でもレタスは一玉が大きいので消費するのになかなか時間がかかるものです。 食べなきゃ食べなきゃと思いつつ、気が付いたときにはもうしなびていて使えなかったことも。 今回はこのしなびたレタスをもう一度シャキッとしたレタスに戻す方法やレタスをなるべく長持ちできる保存方法を紹介したいとおもいます。
- トマト
- 栄養たっぷりでたくさんレシピが豊富なトマトは子供から大人までもみんなすきな食べ物だとおもいます。 そのため、スーパーなどで安くなっているとついついたくさん買ってきてしまう食材で、買いすぎてたまに傷んでしまったりしています。 そこで今回はトマトを長く保存する正しい保存方法をお伝えしていきたいとおもいます。
- 大根
- 実家から新鮮なお野菜が毎日届く中、大根の消費にとても困っていました。 当時は、保存方法がわからず、大根も切ってラップで包み冷凍庫に入れ、数ヶ月以上も放置していました。 もし同じようにお困りの方がいましたら、是非大根の保存方法をまとめましたので参考にしてみてください。
- もやし
- もやしは安いので買い物に行くと必要でなくても買ってしまうこともあるのではないでしょうか。 しかし、特売してるとついつい買いすぎて、使い切れなくて傷んでしまうことがありました。 一人暮らしの学生時代から、主婦になるまで、ずっと助けてもらったもやしの保存方法が、皆さんのお役に立てたらと思います。
- ネギ
- ネギって色々な料理に少しずつ使う事が多いので、私はスーパーで買ってきて冷蔵庫の野菜室にそのままポンッと入れて置いたらしなびたり芯(白ネギの真ん中部分)がにょっきり成長して伸びてしまう事がしょっちゅうでした。 保存方法といっても新聞紙にくるむくらいしか無さそうだし…。 そんな私が調べたネギの保存方法を是非参考にして美味しいネギを召し上がってください。
- なす
- なすはお味噌汁などにいれてもおいしくたべることができて、炒め物にしてもおいしく食べられて、お漬物にしてもおいしく、とても万能な食材です。 ですがなすは間違った保存をしてしまうとすぐに傷んで食べれなくなってしまったりする食材でもあります。 我が家でも正しい保存方法をしらないときは、いつもついつい買いすぎて腐らせてしまうことがたくさんありました。 今回はなすをおいしく、できるだけ長く保存する正しい保存方法を今回はおつたえしていきたいとおもいます。
- ブロッコリー
- ブロッコリーはビタミンCが豊富で食物繊維も含まれているので、便秘解消にぴったり。 コレステロールを抑制する作用やデトックス効果もあるので健康が気になる人にはおすすめの野菜です。 でもブロッコリーはひとふさの量が多いため気がついたら冷蔵庫の中で、黒ずんでいたり、花蕾の部分が黄色くなっていたりしますよね? ブロッコリーはあまり日持ちしないので早く食べることをおすすめしますが、今回はブロッコリーを少しでも長持ちできるように保存方法をまとめてみました。
- 白菜
- 夫婦二人暮らしの生活だったのですが、白菜を丸ごといただいたことがありました。 普段は1/4サイズにカットされた白菜を購入し、すぐに調理してしまっていたので保存方法について詳しく知りませんでした。 そんな時に、農家の方に教えていただいた白菜の保存方法をご紹介したいと思いますので参考にしていただければと思います。
- ごぼう
- 秋に入った頃、スーパーでごぼうを買い、それはそれは美味しく頂いたのですが、ふと見ると、まるまる一本分ごぼうが余りました。しかも土付き。 土は落としてから保存する方がいいのかどうか分かりませんでした。 以下、その時に調べたごぼうの保存方法についてまとめました。
- アボカド
- 私はアボカドが大好きです。 そんな私も、アボカドに慣れるまで?は、熟れ過ぎたものを買ってしまって食べる前にダメにしてしまったり、逆に固いアボカドを買って「なんか違う・・・」とがっかりしたり、、。 そんな失敗を繰り返して、いまではベストなタイミングでアボカドを食べることができるようになりました。 アボカドをお家でも気軽に食べたいなぁと思っている方、ぜひ保存方法を参考にしてみてくださいね。
- バジル
- イタリアンレストランやパスタ専門店にいくと必ずといっても目にするバジル。 バジルの収穫は春から秋といわれていすが、工夫次第で年中、バジルを味わうことも可能です。 今回はそんなバジルの保存方法をまとめてみました。 みなさんもこのレシピでもっと身近にバジルを味わってみませんか?
- パセリ
- パセリは実は栄養価が高く、アンチエイジングにも効果のある野菜です。 でもこのパセリ、購入したのはいいけれど、1回使っただけですぐしなびてヨレヨレになり、そのまま捨ててしまうこと多くありませんか? 今回はパセリをより長持ちさせる保存方法をまとめてみました。
- 青じそ
- ある日、来客が来て、たくさん使うだろうと思い青じそ20枚位入100円位で安く購入したのはよかったんですが、思いのほか10枚で足りてしまいました。 気がついたころには、萎れてしまったり変色しまった青じそがあり、ゴミ箱行きになってしまい困りました。 そこで青じそはどのように保存すれば長持ちするのか調べてみることにしました。
- きのこ
- きのこの保存方法が分からなくて損をしていた時期がありました。 スーパーマーケットなどで売られているきのこのはたいてい冷蔵庫で冷やされています。 ですがきのこは冷蔵じゃなくて冷凍した方が良いのです。 この記事ではきのこの保存方法について解説したいと思います。
- たけのこ
- たけのこって旬が短くて取れると一気にどかっともらったりします。 そうするとどうしても使い切れません。 今回はそんなたけのこを長持ちさせる保存方法を紹介します!
- 春菊
- 私の自宅で、鍋パーティーを10人位でした時に、友人の大好きな春菊を、スーパーでお買い得で安かったため、大量に買い込みました。 しかし大量に余ってしまいました。 そこで、春菊はどうすれば長持ちさせる事が出来るのか、また、美味しい状態で保存出来るのかを、まとめましたので、これから鍋を楽しむ方、ご家庭の方達など、参考にして頂けたらと思います。
- フキ
- 春になるとフキを採って料理して食べるのは美味しくとても嬉しいものです。 しかしフキはアクが強く固くなるのですぐに下処理をしないと美味しく食べることが出来ません。 そこで下処理も含めてフキの保存方法をまとめましたのでぜひ参考にしてください。